わが町知多半島に空港ができました。セントレア空港。いつでも飛んでいけるぞ、空の彼方へ、考えただけで幸せな気分。飛行機見ながら、ちょい福求めてぶらぶら歩いてみようかな、と。
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
松尾寺口からバスに乗り
横山口で下車
そこから矢田寺(やたでら)をめざします
矢田寺へのバスは本数が少ないので
横山口から歩きます、1.5kmほど
 だらだら坂を上っていくと
だらだら坂を上っていくと
山門が見えてきました
 マジ?
マジ?
この後、階段はクネッ、クネッ、クネッ、クネッと
曲がりながら続きます
 まっすぐな参道の奥に
まっすぐな参道の奥に
本堂があります
 矢田寺は今から約1300年前
矢田寺は今から約1300年前
大海人皇子(後の天武天皇)が
壬申の乱の戦勝祈願のために矢田山に上り
即位後、造営させたお寺です
当初、ご本尊は十一面観音と吉祥天女でしたが
後に満米上人によって地蔵菩薩が安置されてからは
地蔵信仰の中心として栄え
ご本尊も地蔵菩薩となりました
参道にも境内にも地蔵石仏がありましたが
撮ったはずなのになぜか消えていました
またいらっしゃい、ということでしょうか?
ここのお地蔵さまは
錫杖を持っていらっしゃいません
矢田型地蔵というらしいです
そうそう
この世とあの世を毎晩行き来していた小野篁さん
満米上人を慕って
しばしば矢田寺に詣でていたそうです
こういう伝説が残っていて
小野篁さんの足跡が感じられるのは感慨深いものがあります
かつてのご本尊、十一面観音さんは
現在は秘仏で
常時拝観はできないようです、残念・・・
 本堂にはどなたもいらっしゃらなかったので
本堂にはどなたもいらっしゃらなかったので
参道の途中にあった大門坊へ
一千体の地蔵尊を安置しているそうです
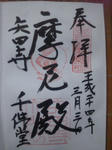 ご朱印は
ご朱印は
大門坊でいただきました
横山口まで戻る途中
塀の上に七福神を発見!(撮影できたのは5体だけでしたが・・)





塀の向こうから
3、4歳くらいの女の子の声がしました
馬場先生にもこのくらいの年のお子さんがいらっしゃるようで
最近の保育園では童謡を教えないんですよね、とおっしゃっていました
童謡もそうですが
唱歌もあまり歌いませんよね
私、息子の小・中・高校の卒業式で
一度も「仰げば尊し」を聞きませんでした
よくわからないJPOPみたいな歌を歌って卒業しました
七福神のお宅では
たぶんこの女の子は「これ、な~に?」と親や祖父母に尋ね
これはね、七福神と言ってね・・・という会話があるんでしょうね
伝承していくということ
それは歴史を伝えていくことでもあるんですが
馬場先生のお話を聞いて・・・
小野篁さんの伝説を知って・・・
そして七福神のいる塀を見て・・・
これってすごく大切なことだな、と改めて思いました
そんなことをつらつら考えながら
次なる神社をめざします
郡山城跡
当世語り部口座第1回 語り部:奈良文化財研究所 馬場基
松尾寺
矢田寺
矢田坐久志玉比古神社
・・・・・・・・・・続く
横山口で下車
そこから矢田寺(やたでら)をめざします
矢田寺へのバスは本数が少ないので
横山口から歩きます、1.5kmほど
山門が見えてきました
この後、階段はクネッ、クネッ、クネッ、クネッと
曲がりながら続きます
本堂があります
大海人皇子(後の天武天皇)が
壬申の乱の戦勝祈願のために矢田山に上り
即位後、造営させたお寺です
当初、ご本尊は十一面観音と吉祥天女でしたが
後に満米上人によって地蔵菩薩が安置されてからは
地蔵信仰の中心として栄え
ご本尊も地蔵菩薩となりました
参道にも境内にも地蔵石仏がありましたが
撮ったはずなのになぜか消えていました
またいらっしゃい、ということでしょうか?
ここのお地蔵さまは
錫杖を持っていらっしゃいません
矢田型地蔵というらしいです
そうそう
この世とあの世を毎晩行き来していた小野篁さん
満米上人を慕って
しばしば矢田寺に詣でていたそうです
こういう伝説が残っていて
小野篁さんの足跡が感じられるのは感慨深いものがあります
かつてのご本尊、十一面観音さんは
現在は秘仏で
常時拝観はできないようです、残念・・・
参道の途中にあった大門坊へ
一千体の地蔵尊を安置しているそうです
大門坊でいただきました
横山口まで戻る途中
塀の上に七福神を発見!(撮影できたのは5体だけでしたが・・)
塀の向こうから
3、4歳くらいの女の子の声がしました
馬場先生にもこのくらいの年のお子さんがいらっしゃるようで
最近の保育園では童謡を教えないんですよね、とおっしゃっていました
童謡もそうですが
唱歌もあまり歌いませんよね
私、息子の小・中・高校の卒業式で
一度も「仰げば尊し」を聞きませんでした
よくわからないJPOPみたいな歌を歌って卒業しました
七福神のお宅では
たぶんこの女の子は「これ、な~に?」と親や祖父母に尋ね
これはね、七福神と言ってね・・・という会話があるんでしょうね
伝承していくということ
それは歴史を伝えていくことでもあるんですが
馬場先生のお話を聞いて・・・
小野篁さんの伝説を知って・・・
そして七福神のいる塀を見て・・・
これってすごく大切なことだな、と改めて思いました
そんなことをつらつら考えながら
次なる神社をめざします
郡山城跡
当世語り部口座第1回 語り部:奈良文化財研究所 馬場基
松尾寺
矢田寺
矢田坐久志玉比古神社
・・・・・・・・・・続く
PR
講座終了後、馬場先生と少しお話をしまして
「この後、稗田町へ行かれては?」とすすめられましたが
私、すでに午後のスケジュールをびっしりと計画していましたので
後ろ髪ひかれながら
奈良交通のバスに乗って、めざす松尾寺(まつおでら)へ
松尾寺口で降りて歩きます
お寺まで2㎞
ちょっと遠いけど
まあ、楽勝でしょう、なんて思っていたら
途中からかなりの上り坂になりまして・・・
実は私、あわててバスに乗ったので昼飯前で・・・
正直、かなりきつかったです、スタミナ切れですね
やはり馬場先生おすすめの稗田町に行くべきだったか?
 でも松尾寺の大黒天さまにぜひ逢いたい
でも松尾寺の大黒天さまにぜひ逢いたい
半ば意地になって
坂を上がりきり
やっとこさ松尾寺に到着
 マジ?
マジ?
 這うようにして
這うようにして
なんとか階段を上りきり
本堂でお参り
ご本尊は千の手と千の眼を持つ厄除観音さま
ご開帳は11月3日のみ
http://www.matsuodera.com/special.html
ここ松尾寺は
718年、天武天皇の皇子、舎人親王が「日本書紀」を編纂されるとき
その完成とご自身の42歳の厄除けの願いをこめて建立されたといわれています
日本最古の厄除け霊場です
日本書紀完成1300年の平成32年(2020年)
馬場先生、またお忙しくなりますね
 三重塔を見上げながら
三重塔を見上げながら
お弁当タイム
 境内の石仏には
境内の石仏には
みな赤い前掛けが・・・
こちらは
千手観音さん
 不動明王さんの
不動明王さんの
前掛け姿・・・可愛いです
午後のスケジュールはかなりタイトなので
ゆっくり休憩している時間はなく
 三重塔に続く階段を上り
三重塔に続く階段を上り
さらに階段を上って
松尾神社へ
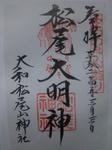 いいお参りでしたと
いいお参りでしたと
ご朱印をいただき
 階段を下り
階段を下り
七福神堂へ
七福の神々が祀られている七福神堂に
私の憧れの大黒天さまが
いらっしゃいます
大黒天さんといえば
たとえば神田明神の大黒天さんならば
福袋をかつぎ
打出の小槌を持ち
にっこり笑った福々しい長者さま・・・ですが
松尾寺の大黒天さんは
福袋こそかついでいますが
眉間に皺をよせ、割とスリム?でいらっしゃる
最古型の大黒天で
なんと弘法大師さまの作と伝えられているそうです
凛々しくて素敵!
足の疲れも一気に吹き飛んでしまいました
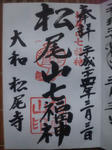 ご朱印は
ご朱印は
七福神でいただきました
そういえば、馬場先生、来年、厄年ですね
しっかりご祈祷なさってください
 松尾寺の帰り道
松尾寺の帰り道
遠くに山焼け後の若草山が見えました
まだまだお寺めぐりは続きます
郡山城跡
当世語り部口座第1回 語り部:奈良文化財研究所 馬場基
松尾寺
矢田寺
矢田坐久志玉比古神社
・・・・・・・・・・続く
「この後、稗田町へ行かれては?」とすすめられましたが
私、すでに午後のスケジュールをびっしりと計画していましたので
後ろ髪ひかれながら
奈良交通のバスに乗って、めざす松尾寺(まつおでら)へ
松尾寺口で降りて歩きます
お寺まで2㎞
ちょっと遠いけど
まあ、楽勝でしょう、なんて思っていたら
途中からかなりの上り坂になりまして・・・
実は私、あわててバスに乗ったので昼飯前で・・・
正直、かなりきつかったです、スタミナ切れですね
やはり馬場先生おすすめの稗田町に行くべきだったか?
半ば意地になって
坂を上がりきり
やっとこさ松尾寺に到着
なんとか階段を上りきり
本堂でお参り
ご本尊は千の手と千の眼を持つ厄除観音さま
ご開帳は11月3日のみ
http://www.matsuodera.com/special.html
ここ松尾寺は
718年、天武天皇の皇子、舎人親王が「日本書紀」を編纂されるとき
その完成とご自身の42歳の厄除けの願いをこめて建立されたといわれています
日本最古の厄除け霊場です
日本書紀完成1300年の平成32年(2020年)
馬場先生、またお忙しくなりますね
お弁当タイム
みな赤い前掛けが・・・
こちらは
千手観音さん
前掛け姿・・・可愛いです
午後のスケジュールはかなりタイトなので
ゆっくり休憩している時間はなく
さらに階段を上って
松尾神社へ
ご朱印をいただき
七福神堂へ
七福の神々が祀られている七福神堂に
私の憧れの大黒天さまが
いらっしゃいます
大黒天さんといえば
たとえば神田明神の大黒天さんならば
福袋をかつぎ
打出の小槌を持ち
にっこり笑った福々しい長者さま・・・ですが
松尾寺の大黒天さんは
福袋こそかついでいますが
眉間に皺をよせ、割とスリム?でいらっしゃる
最古型の大黒天で
なんと弘法大師さまの作と伝えられているそうです
凛々しくて素敵!
足の疲れも一気に吹き飛んでしまいました
七福神でいただきました
そういえば、馬場先生、来年、厄年ですね
しっかりご祈祷なさってください
遠くに山焼け後の若草山が見えました
まだまだお寺めぐりは続きます
郡山城跡
当世語り部口座第1回 語り部:奈良文化財研究所 馬場基
松尾寺
矢田寺
矢田坐久志玉比古神社
・・・・・・・・・・続く
今回は京都から近鉄に乗って奈良入りしました
いつもは名古屋からJR関西本線で
または名古屋から近鉄で
三重県(JRの場合、京都の端っこをかすめますが)を通って奈良に入りますので
京都から近鉄に乗って奈良入りするのは
実は今回が初めてでした
東寺のすぐ横を走っていきます
大和西大寺を過ぎ
垂仁天皇陵が見えてくると
左手側に唐招提寺の杜が広がり
薬師寺が見えてきます
ただ今、東塔は修理中なので
鉄筋の素屋根にすっぽりと覆われていました
と、まもなく近鉄郡山駅に到着
馬場先生の講座までに
1時間近く時間がありましたので
会場近くにある郡山城跡へ
 途中、本家菊屋で
途中、本家菊屋で
御城之口餅をゲット!
 天正年間(1580年代)に
天正年間(1580年代)に
豊臣秀長が
兄の秀吉をもてなすお茶会で
献上された餅菓子です
 「うみゃあでいかんわ」と
「うみゃあでいかんわ」と
お気に召された秀吉が
「鶯餅」と命名したそうな・・・
一口サイズのおいしい鶯餅です
 お雛さまも飾られていて
お雛さまも飾られていて
ついつい
可愛い砂糖菓子も買ってしまいました
ということで
郡山城は秀吉の弟、豊臣秀長の100万石のお城でした
 今は石垣&お堀と
今は石垣&お堀と
 復元された
復元された
櫓と城門があるのみ
最初の城主、筒井順慶は
明智光秀亡きあと、豊臣秀吉VS柴田勝家の衝突に備え
かなり急いで郡山城の守りをかためたようで

 この乱雑な
この乱雑な
野面積みの石垣・・・
郡山や奈良あたりの石をかき集めて積み~の
平城京羅城門の礎石も積み~の
果てはお地蔵さんまで積み~の

そのお地蔵さんは
うつぶせに積まれていて
「逆さ地蔵」と
ガイドブックにも載っていますが
 柳澤神社でご朱印をいただいたときに
柳澤神社でご朱印をいただいたときに
神社の方にお話を聞きましたら
どうも霊媒師が
このお地蔵さんを見つけ出し
ここでお祓いと称して商売していたらしく
「ありがたくもなんともないですよ」とおっしゃっていました
その後、豊臣秀長により郡山城は拡張され
秀長死後、城主はころころ変わり
柳沢吉里が甲府から国替えで郡山城に移ってきてから城下は落ち着き
明治維新まで続いたそうです
 お参りさせていただいた
お参りさせていただいた
柳澤神社ですが
その吉里の父、吉保を祀って創建された神社で
ご朱印を書いてくださった方は
柳沢家の方でした
この柳沢家はとても文化的なお家で
城下は学問はじめ芸術、茶道&華道も栄えたそうです
柳沢文庫は歴史資料も数多く所蔵しており
馬場先生は講座の前にこちらに寄られたそうです
散歩中の犬に飛びつかれたりなどしながら
馬場先生の講座の会場「やまと郡山城ホール」に急ぎました
郡山城跡
当世語り部口座第1回 語り部:奈良文化財研究所 馬場基
松尾寺
矢田寺
矢田坐久志玉比古神社
・・・・・・・・・・続く
いつもは名古屋からJR関西本線で
または名古屋から近鉄で
三重県(JRの場合、京都の端っこをかすめますが)を通って奈良に入りますので
京都から近鉄に乗って奈良入りするのは
実は今回が初めてでした
東寺のすぐ横を走っていきます
大和西大寺を過ぎ
垂仁天皇陵が見えてくると
左手側に唐招提寺の杜が広がり
薬師寺が見えてきます
ただ今、東塔は修理中なので
鉄筋の素屋根にすっぽりと覆われていました
と、まもなく近鉄郡山駅に到着
馬場先生の講座までに
1時間近く時間がありましたので
会場近くにある郡山城跡へ
御城之口餅をゲット!
豊臣秀長が
兄の秀吉をもてなすお茶会で
献上された餅菓子です
お気に召された秀吉が
「鶯餅」と命名したそうな・・・
一口サイズのおいしい鶯餅です
ついつい
可愛い砂糖菓子も買ってしまいました
ということで
郡山城は秀吉の弟、豊臣秀長の100万石のお城でした
櫓と城門があるのみ
最初の城主、筒井順慶は
明智光秀亡きあと、豊臣秀吉VS柴田勝家の衝突に備え
かなり急いで郡山城の守りをかためたようで
野面積みの石垣・・・
郡山や奈良あたりの石をかき集めて積み~の
平城京羅城門の礎石も積み~の
果てはお地蔵さんまで積み~の
そのお地蔵さんは
うつぶせに積まれていて
「逆さ地蔵」と
ガイドブックにも載っていますが
神社の方にお話を聞きましたら
どうも霊媒師が
このお地蔵さんを見つけ出し
ここでお祓いと称して商売していたらしく
「ありがたくもなんともないですよ」とおっしゃっていました
その後、豊臣秀長により郡山城は拡張され
秀長死後、城主はころころ変わり
柳沢吉里が甲府から国替えで郡山城に移ってきてから城下は落ち着き
明治維新まで続いたそうです
柳澤神社ですが
その吉里の父、吉保を祀って創建された神社で
ご朱印を書いてくださった方は
柳沢家の方でした
この柳沢家はとても文化的なお家で
城下は学問はじめ芸術、茶道&華道も栄えたそうです
柳沢文庫は歴史資料も数多く所蔵しており
馬場先生は講座の前にこちらに寄られたそうです
散歩中の犬に飛びつかれたりなどしながら
馬場先生の講座の会場「やまと郡山城ホール」に急ぎました
郡山城跡
当世語り部口座第1回 語り部:奈良文化財研究所 馬場基
松尾寺
矢田寺
矢田坐久志玉比古神社
・・・・・・・・・・続く
カレンダー
| 06 | 2025/07 | 08 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
きょうのお月さん
カテゴリー
最新記事
(05/01)
(04/30)
(04/29)
(04/28)
(04/27)
(04/26)
(04/25)
(04/24)
(04/23)
(04/22)
コメントありがとうございます
[10/26 madamyam]
[10/26 蟹満寺薬師徳光和夫]
[04/29 madamyam]
[04/28 おにぎりヴィヴァルディ]
[04/28 madamyam]
アーカイブ
ブログ内検索
プロフィール
HN:
madamyam
性別:
女性
趣味:
旅行 お寺めぐり
カウンター
